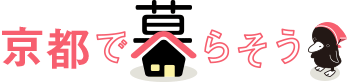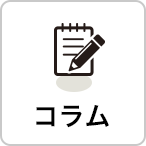京都の神社・お寺のご利益一覧便利帖
-
 誓願寺
誓願寺
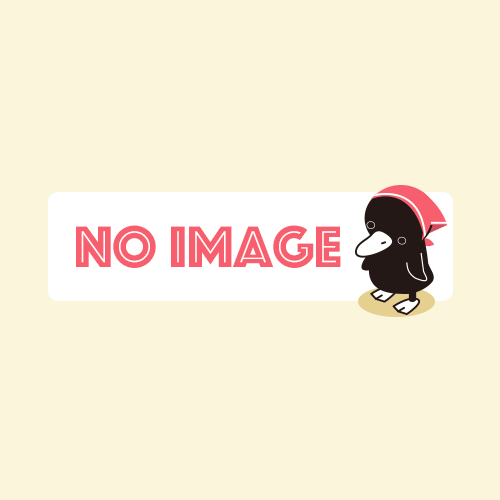
- 住所:京都市中京区新京極通三条下ル桜之町453番地
- アクセス:市バス「河原町三条」「河原町四条」より徒歩5分
地下鉄「京都市役所前駅」より徒歩5分
阪急電車「河原町駅」より徒歩5分
京阪電車「三条駅」より徒歩10分 - 電話番号:075-221-0958
-
 大石神社
大石神社
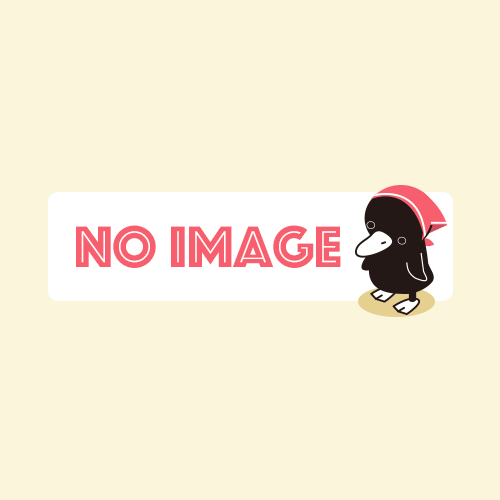
【創建・由緒】 昭和十年、赤穂義士 大石内蔵助良雄の義挙を顕彰するため、大石内蔵助良雄公をご祭神として、大石隠棲の地に京都府知事を会長とする大石神社建設会、山科義士会、また当時浪曲界の重鎮であった吉田大和之丞 (奈良丸) を会長とするもの等の団体が組織され、全国の崇敬者により創建された。
- 住所:京都市山科区西野山桜ノ馬場町116
- アクセス:京阪バス「大石神社前」より徒歩1分
- 電話番号:075-581-5645
- 営業時間:9:00~17:00
- 休業日:無休
- 価格帯:【境内】【宝物殿】ともに無料
-
 地主神社
地主神社
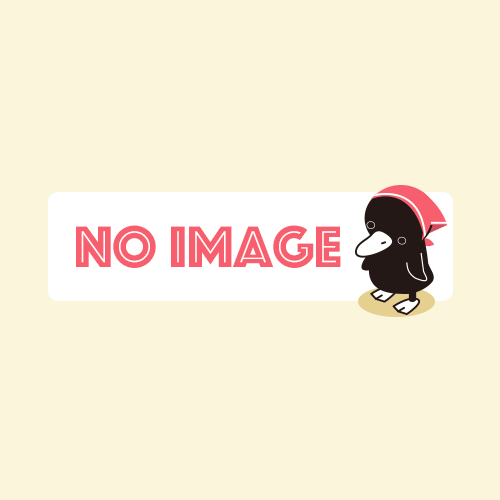
【創建・由緒】 地主神社の創建年代は神代(かみよ:日本の建国以前)とされ、近年の研究により「恋占いの石」が縄文時代の遺物であることが確認されている。 嵯峨天皇・円融天皇・白河天皇と歴代天皇が行幸、皇室との関係が深まり、970年には臨時祭・地主祭りを仰せつかる。その後、中世になると、謡曲『田村』『熊野』をはじめ『梁塵秘抄』『閑吟集』など、有名文学にたびたび登場。「地主権現」の名が、ご利益ある神様として全国に知られるようになる。 古文書によると、戦国期から江戸期にかけては「恋占いの石」に興じる老若男女で境内が一日中にぎわったと、当時の反映の様子が記されている。また、地主神社祈り杉での「丑の刻参り」が大流行した。現在もなお、縁結びの神としてご神徳は全国的に有名。
- 住所:京都市東山区清水一丁目317
- アクセス:市バス「五条坂」「清水道」より徒歩10分
京阪「清水五条」駅より徒歩30分 - 電話番号:075-541-2097
- 営業時間:9:00~17:00
- 休業日:無休
- 価格帯:境内参拝自由
但し、清水寺境内通り抜けにつき、清水寺拝観料が必要
-
 仁和寺
仁和寺
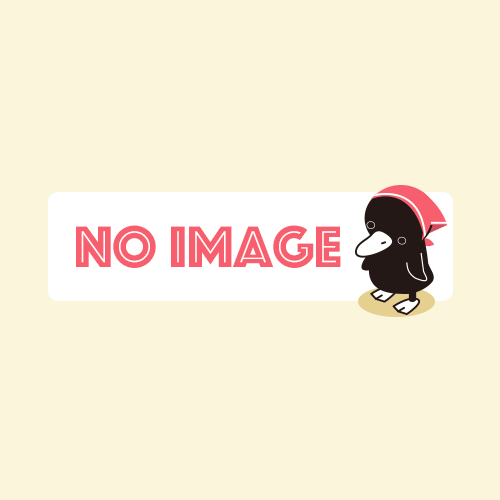
【創建・由緒】 真言宗御室派総本山。仁和2年(886年)第58代光孝天皇が「西山御願寺」と称する一寺の建立を発願したことに始まる。 しかし翌年、光孝天皇は志半ばにして崩御したため、第59代宇多天皇が先帝の遺志を継ぎ、仁和4年(888年)に完成。寺号も元号から仁和寺となった。 応仁の乱(1467年)で焼失。寛永期、覚深(かくしん)法親王(後陽成天皇第一皇子)が徳川家光の援助で再興。同時期の皇居建替えに伴い、旧皇居の紫宸殿・清涼殿・常御殿などが仁和寺に下賜され、境内に移築された。 仁和寺御殿は、常御殿を移築したものであったが、明治期に焼失。現在の建物は明治期末〜大正初期に再建されたもの。 平成6年(1994年)に古都京都の文化財の1つとしてユネスコの「世界遺産」に登録。 【庭園の特徴】観賞式
- 住所:京都市右京区御室大内33
- アクセス:京福電鉄北野線「御室」駅より徒歩10分
市バス「御室仁和寺前」より徒歩1分 - 電話番号:075-461-1155
- 営業時間:【御殿】 3~11月/9:00~17:00 12~2月/9:00~16:30 ※いずれも閉門30分前受付終了 【霊宝館】 9:00~16:30 春季/4月1日~5月第4日曜日まで 秋季/10月1日~11月23日まで
- 休業日:無休
- 価格帯:【御殿】大人・高校生:400円/小・中学生:300円
【霊宝館(期間限定)】大人:500円/中・高校生:300円
【茶室〈遼廓亭・飛濤亭〉特別拝観】1,000円
※別途、御殿拝観料も必要。5名様以上で7日前までに要予約
【特別入山料(御室桜開花期間)】大人・高校生:500円/小・中学生:200円
-
 御香宮神社
御香宮神社
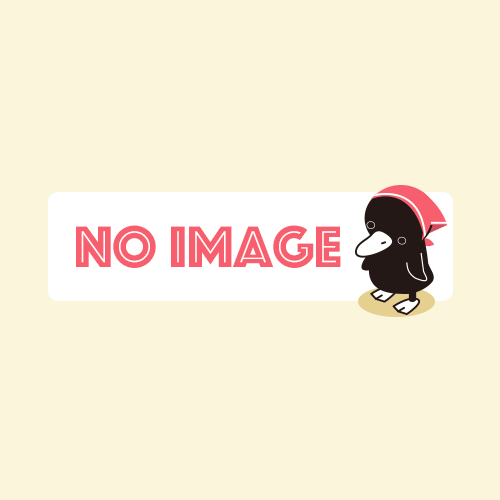
- 住所:京都市伏見区御香宮門前町174
- アクセス:市バス「御香宮前」より徒歩1分
京阪「伏見桃山」駅より徒歩5分
近鉄「桃山御陵前」駅より徒歩5分 - 電話番号:075-611-0559
- 営業時間:9:00~16:00
- 休業日:不定休
- 価格帯:大人/200円
大学生/150円
小人~高校生/100円