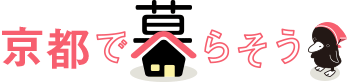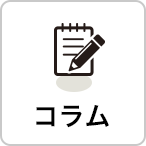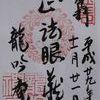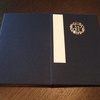除夜の鐘を撞ける京都のお寺
最近年末は遠くで聞こえる鐘の音を聞いたり、TVで見て過ごす人らも多いみたいやけど、せっかく京都にはぎょうさんお寺があるんどす。近すぎてありがたみを忘れてしまいがちやけど、わざわざお寺を見るために全国から来はる人もいてはるんよ? わてらが行かへんのんはもったいないと思いまへんか?
今年は初詣の前に自分で鐘ついて、新しい年を迎えまひょ。
-
 鞍馬寺
鞍馬寺
【創建・由緒】 鞍馬弘教総本山。宝亀1年(770)鑑真和上の高弟鑑禎(がんてい)上人が毘沙門天を本尊として奉安したことを起源とする。 平安時代は京都の北方守護の寺として信仰を集めた。本殿金堂・多宝塔などは近年再建され、鉄筋コンクリート造り。 境内の「鞍馬山霊宝殿」の1階は、山内の動植物・鉱物などを展示する自然科学博物苑展示室、2階は寺宝展観室と與謝野晶子の遺品を展示する與謝野記念室、3階は国宝の毘沙門天像などの仏像奉安室・宝物収蔵庫がある。 本殿裏から奥の院への山道に牛若丸の遺跡がある。
- 住所:京都市左京区鞍馬本町1074
- アクセス:叡山電車「鞍馬駅」より徒歩約5分
山頂の本殿までは、更にケーブル2分と徒歩10分
または徒歩30分 - 電話番号:075-741-2003
- 営業時間:9:00~16:30
- 休業日:無休 (霊宝殿は月曜、12月12日~2月末日休館)
- 価格帯:【一般】
高校生以上/200円
中学生以下/無料
【団体割引】
20~49人/160円
50~99人/120円
100人以上/100円
【障害者】
本人は無料
-
 東福寺
東福寺
重森三玲による作庭。「八相成道(釈迦の生涯で起きた8つの重要な出来事)」を方丈の四方を庭で囲んで表現している。その東西南北の四つの庭園を総称し「八相の庭」という。 【南庭】 蓬莱神仙の世界、九山八海の須弥山を現している。東(左手)に巨石にて四神仙島(仙人が住む4つの島)の、「方丈」、「蓬莱」、「瀛州(えいしゅう)」、「壷梁(こりょう)」を、その周りの波紋は「八海」、西(右手)の築山は「五山(天竜寺、相国寺、建仁寺、東福寺、万寿寺)」を表現。この庭だけで八相成道のうちの6つが表現されている。 【西庭】「井田の庭」 八相成道の「井田市松(せいでんいちまつ)」を表現。井田とは、井の字に等分した中国の土地制度に因んだもの。切り石を縁石にした葛石で井の字(大桝形)に組み、正方形に刈り込んだサツキ、白砂により市松模様が作られている。 【東庭】「北斗七星の庭」 八相成道の「北斗七星」を表現した庭。東司(とうす・トイレ)に使われていた柱石を利用して北斗七星を構成し、それを雲文様地割に配し小宇宙空間を表している。後方には天の川を表したという植栽が配置されている。 【北庭】「市松の庭」 苔地に敷石を市松模様に配置した庭。苔の青みと敷石のコントラストが美しい。西から東へ仏法が広がる様を表しているとされ、東へ移るほど市松紋が次第にぼかされている。
- 住所:京都市東山区本町15丁目778
- アクセス:京阪、JR「東福寺駅」より南東へ徒歩10分
市バス「東福寺」より徒歩5分 - 電話番号:075-561-0087
- 営業時間:9:00~16:00
- 休業日:方丈庭園のみ12/31~1/1休み 境内は無休無料で拝観可
- 価格帯:大人/400円
中学生/300円
小人/300円
-
 天龍寺
天龍寺
龍門瀑 鯉魚石 水落石 橋石組 現存する日本最古の石橋 借景 回遊式 曹源池
- 住所:京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町68
- アクセス:JR「嵯峨嵐山駅」より徒歩10分
- 電話番号:075-881-1235
- 営業時間:8:30~17:30
- 休業日:無休
- 価格帯:大人/500円
小・中学生/300円
-
 禅林寺(永観堂)
禅林寺(永観堂)
「モミジの永観堂」と親しまれている京都有数の古刹です。
- 住所:京都市左京区永観堂町48
- アクセス:市バス「南禅寺永観堂道」より徒歩約3分
- 電話番号:075-761-0007
- 営業時間:9:00~17:00 (受付は16:00まで)
- 休業日:無休
- 価格帯:一 般/600円
小・中・高生/400円
-
 高台寺
高台寺
豊臣秀吉没後、正妻の北政所(ねね、出家して高台院)が菩提を弔うため、徳川家康の援助を得て1660年に開創した寺。 【北庭】 書院と開山堂との間に配置された臥龍池と、開山堂と霊屋との間に配置された偃月池、この2つの池を中心とした池泉回遊式庭園。「鶴亀の庭」とも呼ばれ、東山の山々を借景とし、豊臣秀吉遺愛の観月台から見て北側に亀島、南側の岬に鶴島の石組みが配置されている。 【波心庭】(南庭) 枯山水式。主に白砂と立砂により構成され、西に植えられた枝垂桜が知られている。 その他の見どころとしては伏見城から移築された安土・桃山時代の茶室・傘亭、時雨亭など。 傘亭の天井は、丸太と竹とで組まれ、唐傘を表したことから傘亭と呼ばれた。茶室は一般的に天井が低いものが多いが、傘亭の天井は高い。また、時雨亭は二階建ての造りで、茶室としては珍しい構造になっている。
- 住所:京都市東山区下河原町526
- アクセス:市バス「東山安井」より東へ徒歩5分
- 電話番号:075-561-9966
- 営業時間:9:00~17:00 受付終了(17:30 閉門)
- 休業日:無休
- 価格帯:大人/600円 (掌美術館を含む)
中高生/250円
-
 青蓮院
青蓮院
- 住所:京都市東山区粟田口三条坊町69-1
- アクセス:市バス「神宮道」より徒歩2分
地下鉄「東山駅」より徒歩5分 - 電話番号:075-561-2345
- 営業時間:9:00~17:00(16:30受付終了)
- 休業日:無休
- 価格帯:大人500円
中高生400円
小学生200円
-
 南禅寺
南禅寺
方丈庭園:虎の児渡し 借景
- 住所:京都市左京区南禅寺福地町
- アクセス:市バス法勝寺町又は南禅寺永観堂道前下車
- 電話番号:075-771-0365
- 営業時間:[12/1~2/28] 8:40~16:30 [3/1~11/30] 8:40~17:00 ※ 拝観受付は拝観時間終了の20分前までとします。 ※ 年末(12月28日~31日)は一般の拝観をお断りします。 ※ 年始は休みません。
- 休業日:12/28~12/31
- 価格帯:一 般/500円
高校生/400円
小中学生/300円
-
 千本ゑんま堂 引接寺
千本ゑんま堂 引接寺
【創建・由緒】 高野山真言宗。小野篁(おのの たかむら)が開基。寛仁期、恵心僧都の法弟、定覚(じょうかく)上人が創建。 百人一首の歌人として知られる小野篁(802~853)は、この世とあの世を行き来する神通力を有したとされており、昼は宮中に赴き、夜は閻魔之廰に仕えたとの伝説を残している。 篁は閻魔法王より現世浄化のため、塔婆を用いて亡き先祖を再びこの世へ迎える供養法で、後に我が国の伝統習慣である「盂蘭盆会(お盆行事)」へと融合発展する法儀「精霊迎えの法」を授かった。その根本道場として、朱雀大路(現・千本通り)の北側に篁自ら閻魔法王の姿を刻み建立した祠が、開基とされる。
- 住所:京都市上京区千本通寺之内上る閻魔前町34番地
- アクセス:市バス「千本鞍馬口」より南へ徒歩すぐ
市バス「乾隆校前」より北へ徒歩すぐ - 電話番号:075-462-3332
- 営業時間:境内参拝自由
- 休業日:無休
- 価格帯:境内参拝自由
-
 醍醐寺
醍醐寺
【創建・由緒】 真言宗醍醐派の総本山。貞観16年(874)聖宝が山上に草庵を結び准胝(じゅんてい)如意輪両観音像を彫刻・安置したのが始まり(上醍醐)。 延長4年(926)下醍醐が開かれ、釈迦堂、五重塔などを建立。応仁・文明の乱の戦火で五重塔を除く堂塔伽藍を焼失したが、慶長3年(1598)豊臣秀吉の花見をきっかけに再興された。 上醍醐の准胝堂は西国三十三ヵ所第11番札所だが、2008年に落雷により焼失。納経は現在、金堂で行われている。 創建時の五重塔、桃山時代に移築された金堂、および上醍醐の薬師堂はいずれも国宝。絵画では絹本著色五大尊像(国宝)など多数の文化財を所蔵。2月23日の五大力さん、4月第2日曜日の豊太閤花見行列は有名。1994年(平成6)12月「古都京都の文化財」として、「世界遺産条約」に基づく世界文化遺産に登録された。 【三宝院庭園・見どころ】 鶴亀蓬莱形式、回遊式、舟遊式、建物からの観賞式 信長・秀吉愛好の名石「藤戸石」 三段の滝、三尊石組
- 住所:京都市伏見区醍醐東大路町22
- アクセス:京阪バス「醍醐三宝院」下車すぐ
地下鉄「醍醐駅」より徒歩10分 - 電話番号:075-571-0002
- 営業時間:※いずれも閉門の30分前に受付終了 【三宝院庭園・伽藍】 3月から12月第1日曜日までの期間/9:00~17:00 12月第1日曜日の次の日~2月末までの期間/9:00~16:00 【上醍醐】 夏期(3月1日~11月末)/9:00~16:00 冬期(12月1日~ 2月末日)/9:00~15:00 【霊宝館】※開館日は月ごとに変わる為、公式サイトで要確認 1月・2月/9:00~16:00 3月~11月/9:00~17:00
- 休業日:無休
- 価格帯:【三宝院・伽藍・霊宝館・上醍醐それぞれ】
個人 大人:600円/中・高校生:300円
団体(30名以上)大人:400円/小人:200円
※小学生以下は無料
-
 正覚山實相寺(実相寺)
正覚山實相寺(実相寺)
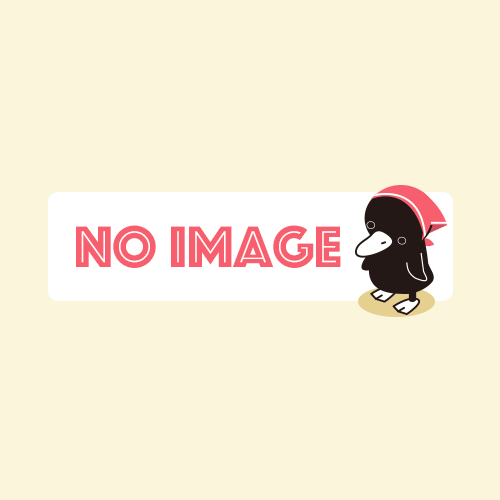
- 住所:京都市南区上鳥羽鍋ヶ渕町10
- アクセス:市バス「城ヶ前町」下車すぐ
市バス「上鳥羽下車」下車徒歩5分
近鉄京都線「上鳥羽駅」より徒歩20分
近鉄・地下鉄「竹田駅」よりタクシー5分
JR「京都駅」よりタクシー15分 - 電話番号:075-691-9648
- 営業時間:8:00~17:00