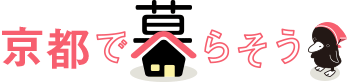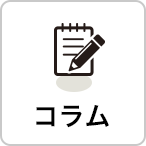【2017年版】京都で紅葉のライトアップ見学・夜間拝観ができる名所
そこでこの時期、毎年行われている紅葉ライトアップを見学できる寺社仏閣・スポットを一挙ご紹介します。
読書やスポーツもいいけれど、秋の夜長、ちょっと出かけてみませんか!
-
 京都・嵐山花灯路
京都・嵐山花灯路
- 住所:京都府京都市右京区嵯峨天龍寺造路町
- アクセス:嵐電嵐山駅・阪急嵐山駅・JR嵯峨嵐山駅よりすぐ
- 営業時間:2017年12月8日(金)~2017年12月17日(日)17:00〜20:30
-
 大覚寺(旧嵯峨御所 大覚寺門跡)
大覚寺(旧嵯峨御所 大覚寺門跡)
【創建・由緒】 弘法大師空海を宗祖と仰ぐ真言宗大覚寺派の本山。正式には旧嵯峨御所大覚寺門跡と称し、嵯峨御所とも呼ばれる。平安初期、嵯峨天皇が檀林皇后とのご成婚の新室である離宮を建立されたが、これが大覚寺の前身・離宮嵯峨院である。 嵯峨院が大覚寺となったのは、皇孫である恒寂(つねさだ)入道親王を開山として開創した貞観18年(876年)。嵯峨天皇の長女・正子内親王が大覚寺と号した。 弘法大師空海のすすめにより嵯峨天皇が浄書された般若心経が勅封(60年に1度の開封)として奉安され、般若心経写経の根本道場として知られる。明治時代初頭まで、代々天皇もしくは皇統の方が門跡(住職)を務めた格式高い門跡寺院である。 応仁の乱で衰退後、天正期の空性、元和期の尊性の時代に、衰退した大覚寺の再建に取りかかり、寛永期にはほぼ寺観が整えられた。 いけばな発祥の花の寺でもあり、「いけばな嵯峨御流」の総司所(家元)でもある。 【庭園見どころ】 日本最古の滝石組・名古曾(なこそ)の滝/遣水/夜泊石/庭湖石/神仙蓬莱思想
- 住所:京都市右京区嵯峨大沢町4
- アクセス:市バス・京都バス「大覚寺」すぐ
JR「嵯峨嵐山駅」より徒歩約15分 - 電話番号:075-871-0071
- 営業時間:9:00~17:00(16:30受付終了)
- 休業日:無休(寺内行事により内拝不可日あり)
- 価格帯:大人/500円
小・中・高/300円
-
 北野天満宮
北野天満宮
京都市上京区、菅原道真をおまつりした神社です。学問の神様としても有名。また、「梅苑」は約2万坪の境内に約1,500本もの梅の木があり、毎年2月~3月には美しい梅の花を観賞できます。
- 住所:京都市上京区馬喰町 北野天満宮社務所
- アクセス:市バス「北野天満宮前」よりすぐ
嵐電「白梅町」駅より徒歩5分 - 電話番号:075-461-0005
- 営業時間:4月~9月 5:00~18:00 10月~3月 5:30~17:30 ※拝観自由
-
 神護寺
神護寺
- 住所:京都市右京区梅ヶ畑高雄町5番地
- アクセス:JR京都駅、地下鉄烏丸線京都駅からJRバス「高雄・京北線」で約50分、「山城高雄」下車、徒歩約20分
阪急京都線烏丸駅、地下鉄烏丸線四条駅から市バス8号系統で約45分、「高雄」下車、徒歩約20分 - 電話番号:075-861-1769
- 営業時間:拝観時間 9:00~16:00
- 休業日:年中無休
- 価格帯:中・高・大学・大人600円
小学生300円
-
 貴船神社
貴船神社
燈籠が並ぶ石段で有名な貴布禰総本宮。また「恋を祈る社」として名高く、えんむすびにも。
- 住所:京都市左京区鞍馬貴船町180
- アクセス:京都バス「貴船」より徒歩5分
叡電「貴船口」駅より徒歩30分 - 電話番号:075-741-2016
- 営業時間:6:00~20:00(5月~11月) 6:00~18:00(12月~4月)
- 休業日:無休
-
 醍醐寺
醍醐寺
【創建・由緒】 真言宗醍醐派の総本山。貞観16年(874)聖宝が山上に草庵を結び准胝(じゅんてい)如意輪両観音像を彫刻・安置したのが始まり(上醍醐)。 延長4年(926)下醍醐が開かれ、釈迦堂、五重塔などを建立。応仁・文明の乱の戦火で五重塔を除く堂塔伽藍を焼失したが、慶長3年(1598)豊臣秀吉の花見をきっかけに再興された。 上醍醐の准胝堂は西国三十三ヵ所第11番札所だが、2008年に落雷により焼失。納経は現在、金堂で行われている。 創建時の五重塔、桃山時代に移築された金堂、および上醍醐の薬師堂はいずれも国宝。絵画では絹本著色五大尊像(国宝)など多数の文化財を所蔵。2月23日の五大力さん、4月第2日曜日の豊太閤花見行列は有名。1994年(平成6)12月「古都京都の文化財」として、「世界遺産条約」に基づく世界文化遺産に登録された。 【三宝院庭園・見どころ】 鶴亀蓬莱形式、回遊式、舟遊式、建物からの観賞式 信長・秀吉愛好の名石「藤戸石」 三段の滝、三尊石組
- 住所:京都市伏見区醍醐東大路町22
- アクセス:京阪バス「醍醐三宝院」下車すぐ
地下鉄「醍醐駅」より徒歩10分 - 電話番号:075-571-0002
- 営業時間:※いずれも閉門の30分前に受付終了 【三宝院庭園・伽藍】 3月から12月第1日曜日までの期間/9:00~17:00 12月第1日曜日の次の日~2月末までの期間/9:00~16:00 【上醍醐】 夏期(3月1日~11月末)/9:00~16:00 冬期(12月1日~ 2月末日)/9:00~15:00 【霊宝館】※開館日は月ごとに変わる為、公式サイトで要確認 1月・2月/9:00~16:00 3月~11月/9:00~17:00
- 休業日:無休
- 価格帯:【三宝院・伽藍・霊宝館・上醍醐それぞれ】
個人 大人:600円/中・高校生:300円
団体(30名以上)大人:400円/小人:200円
※小学生以下は無料
-
 知恩院
知恩院
【創建・由緒】 浄土宗総本山。宗祖法然上人が、承安5年(1175)東山大谷の吉水に設けた草庵に始まる。その後、二代源智上人により基礎が築かれ、文暦期、源智(勢観房)が復興(大谷寺)、その後火災や兵乱に遭い、徳川家康・秀忠・家光により現在の壮大な伽藍が形成された。三門・経蔵・勢至堂を除いては、寛永期の再建。 【見どころ】 法然上人の像を安置する御影堂(国宝)は1639年(寛永16)建立になる大建築で、大方丈、小方丈、勢至堂、経蔵、三門(国宝)、唐門、大鐘楼、集会堂、大庫裡、小庫裡と文化財指定建造物が並ぶ。 三門(国宝)はわが国最大木造の門で近年解体修理され偉観をとりもどした。大小方丈前の方丈庭園(回遊式庭園)は、僧玉淵坊作と伝えられる。国宝の紙本着色法然上人絵伝(48巻伝)、阿弥陀二十五菩薩来迎図など多数の文化財を所蔵。 【方丈庭園】 江戸初期、小堀遠州と縁のある僧、玉淵により作庭。池泉回遊式の庭園。 【二十五菩薩の庭】 皐月の低い刈込と石で構成。知恩院が所有している阿弥陀如来二十五菩薩来迎図に由来。石は阿弥陀如来と二十五菩薩を、植え込みは来迎雲を表していると言われている。
- 住所:京都市東山区林下町400
- アクセス:市バス「知恩院前」より徒歩約5分(円山公園のすぐ北側)
- 電話番号:075-531-2111
- 営業時間:9:00~16:30(16:00受付終了)
- 休業日:方丈庭園:御影堂修理工事および御廟所防災設備工事に伴い拝観休止中(平成23年5月8日~)
- 価格帯:【境内】無料
【庭園】大人(高校生以上)300円/小人150円
-
 宝泉院
宝泉院
血天井 水琴窟 老松
- 住所:京都市左京区大原勝林院町187
- アクセス:京都バス「大原」より徒歩約15分
- 電話番号:075-744-2409
- 営業時間:9:00~17:00
- 休業日:無休
- 価格帯:大人/800円
中・高/700円
小/600円
-
 南禅寺/天授庵
南禅寺/天授庵
- 住所:京都府京都市左京区南禅寺福地町86-8
- アクセス:市バス「法勝寺町」より徒歩約5分
地下鉄「蹴上駅」より徒歩約5分 - 電話番号:075-771-0744
- 営業時間:9:00~17:00
- 休業日:11/11午後~11/12午前中 その他臨時行事のため休みあり
- 価格帯:大人(大学生)/400円
高校生/300円
小・中学生/200円