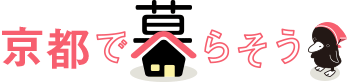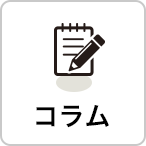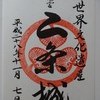梅を見に行こう!京都のおすすめ観梅スポット
京都はまだまだ寒い日が続きます。暖かくしておでかけくださいね。
-
 梅宮大社
梅宮大社
【創建・由緒】 橘氏の祖・諸兄(モロエ)公の母、県犬養三千代(アガタイヌカイ ミチヨ)が、橘氏一門の氏神として相楽郡井手に祀った神社。平安遷都後、檀林(だんりん)皇后(嵯峨天皇の后・橘 嘉智子(たちばな かちこ)が現在地に移転。主な建物は元禄期焼失、すぐに再建された。
- 住所:京都市右京区梅津フケノ川町30
- アクセス:市バス「梅ノ宮神宮前」より徒歩3分
阪急「松尾大社」駅より徒歩15分 - 電話番号:075-861-2730
- 営業時間:9:00~17:00
- 休業日:無休
- 価格帯:大人:500円/小人:250円
-
 北野天満宮
北野天満宮
京都市上京区、菅原道真をおまつりした神社です。学問の神様としても有名。また、「梅苑」は約2万坪の境内に約1,500本もの梅の木があり、毎年2月~3月には美しい梅の花を観賞できます。
- 住所:京都市上京区馬喰町 北野天満宮社務所
- アクセス:市バス「北野天満宮前」よりすぐ
嵐電「白梅町」駅より徒歩5分 - 電話番号:075-461-0005
- 営業時間:4月~9月 5:00~18:00 10月~3月 5:30~17:30 ※拝観自由
-
 二条城
二条城
【創建・由緒】 慶長8年(1603)徳川将軍家康が京都御所の守護と将軍上洛のときの宿泊所として造営し、3代将軍家光により伏見城の遺構を移すなどして、寛永3年(1626)に完成。 家康が建てた慶長年間の建築と、家光がつくらせた絵画・彫刻などが総合されて、いわゆる桃山時代様式の全貌を垣間見ることが出来る。 【見所】 二の丸庭園:護岸石組 鶴島亀島、神仙蓬莱、座視観賞式、廻遊式、三尊石組
- 住所:京都市中京区二条通堀川西入二条城町541
- アクセス:地下鉄「二条城前駅」下車すぐ
- 電話番号:075-841-0096
- 営業時間:【開城時間】 8:45~16:00(閉城17:00) 【二の丸御殿 観覧時間】 9:00~16:00
- 休業日:毎年7月・8月・12月・1月の毎週火曜日 (ただし休日の場合は翌日) 年末年始:12月26日~1月4日
- 価格帯:一般/600円
中学生・高校生/350円
小学生/200円
-
 城南宮
城南宮
【創建・由緒】 平安遷都の際に、国土の安泰と都の守護を願って、王城(都)の南に祀られたお宮であることから、城南宮と称えられる。 応仁の乱などで荒廃したが、江戸期に復興。 【御祭神】 国常立尊(くにのとこたちのみこと) 八千矛神=大国主命(やちほこのかみ=おおくにぬしのみこと) 息長帯日売命=神功皇后(おきながたらしひめのみこと=じんぐうこうごう)
- 住所:京都市伏見区中島鳥羽離宮町7
- アクセス:市バス「城南宮道」より徒歩3分
京阪バス「城南宮東口」より徒歩3分
地下鉄・近鉄「竹田」駅より徒歩15分
京都らくなんエクスプレス(土日祝)「城南宮前」より徒歩1分
京都らくなんエクスプレス(平日)「油小路城南宮」より徒歩4分 - 電話番号:075-623-0846
- 営業時間:【境内】参拝自由 【神苑拝観】9:00~16:30(受付16:00)
- 休業日:無休
- 価格帯:【境内】参拝自由
【神苑・楽水苑】大人:500円/小・中学生:300円/団体(20名以上):450円
-
 京都御所
京都御所
- 住所:京都府京都市上京区京都御苑3
- アクセス:地下鉄 丸太町下車 徒歩約15分
市バス 府立医大病院前下車 徒歩約10分 - 電話番号:075-211-1215
- 営業時間:事前予約制
- 休業日:事前予約制 日曜日、土曜日、国民の祝日・休日 ※ただし、土曜日については、下記のとおりに拝観を実施。 ・3月、4月、5月、10月、11月の毎土曜日 ・その他の月の第3土曜日 年末年始(12月28日~翌年1月4日) その他行事ある日
- 価格帯:無料
-
 大覚寺(旧嵯峨御所 大覚寺門跡)
大覚寺(旧嵯峨御所 大覚寺門跡)
【創建・由緒】 弘法大師空海を宗祖と仰ぐ真言宗大覚寺派の本山。正式には旧嵯峨御所大覚寺門跡と称し、嵯峨御所とも呼ばれる。平安初期、嵯峨天皇が檀林皇后とのご成婚の新室である離宮を建立されたが、これが大覚寺の前身・離宮嵯峨院である。 嵯峨院が大覚寺となったのは、皇孫である恒寂(つねさだ)入道親王を開山として開創した貞観18年(876年)。嵯峨天皇の長女・正子内親王が大覚寺と号した。 弘法大師空海のすすめにより嵯峨天皇が浄書された般若心経が勅封(60年に1度の開封)として奉安され、般若心経写経の根本道場として知られる。明治時代初頭まで、代々天皇もしくは皇統の方が門跡(住職)を務めた格式高い門跡寺院である。 応仁の乱で衰退後、天正期の空性、元和期の尊性の時代に、衰退した大覚寺の再建に取りかかり、寛永期にはほぼ寺観が整えられた。 いけばな発祥の花の寺でもあり、「いけばな嵯峨御流」の総司所(家元)でもある。 【庭園見どころ】 日本最古の滝石組・名古曾(なこそ)の滝/遣水/夜泊石/庭湖石/神仙蓬莱思想
- 住所:京都市右京区嵯峨大沢町4
- アクセス:市バス・京都バス「大覚寺」すぐ
JR「嵯峨嵐山駅」より徒歩約15分 - 電話番号:075-871-0071
- 営業時間:9:00~17:00(16:30受付終了)
- 休業日:無休(寺内行事により内拝不可日あり)
- 価格帯:大人/500円
小・中・高/300円
-
 随心院
随心院
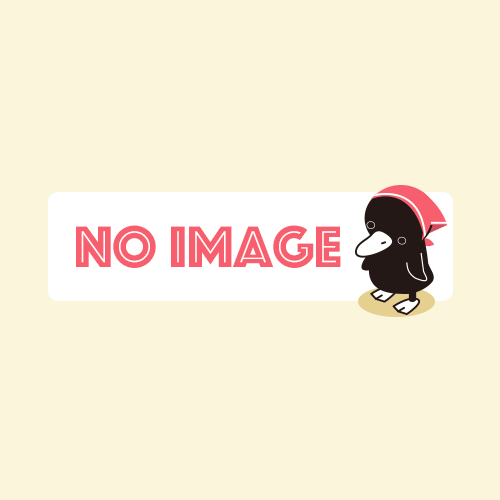
観賞式
- 住所:京都市山科区小野御霊町35
- アクセス:市バス「小野」又は地下鉄「小野駅」より徒歩3分
- 電話番号:075-571-0025
- 営業時間:9:00~16:30
- 休業日:無休
- 価格帯:大人/400円
中学生/300円
-
 常寂光寺
常寂光寺
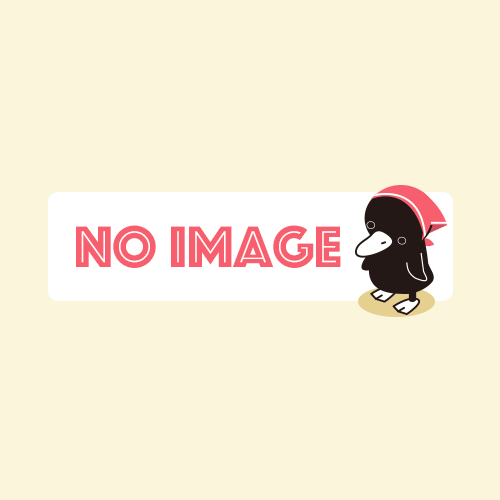
- 住所:京都市右京区嵯峨小倉山小倉町3
- アクセス:京福「嵐山駅」より徒歩25分
市バス・京都バス「嵯峨小学校前」より徒歩15分 - 電話番号:075-861-0435
- 営業時間:9:00~17:00 (16:30受付終了)
- 休業日:無休
-
 勧修寺
勧修寺
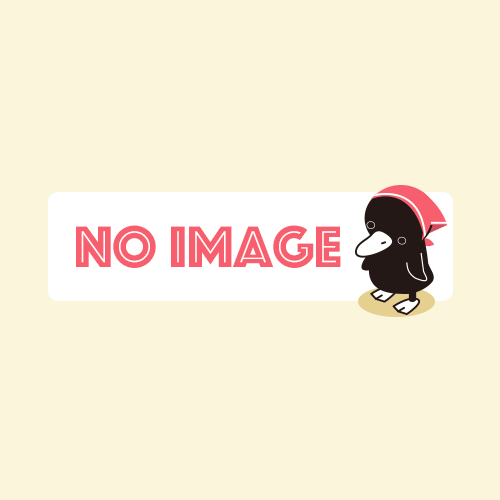
舟遊式
- 住所:京都府京都市山科区勧修寺仁王堂町27−6
- アクセス:京阪バス「勧修寺」下車すぐ
地下鉄東西線小野駅下車徒歩約5分 - 電話番号:075-571-0048
- 営業時間:9:00~16:00
- 休業日:無休
- 価格帯:大人/400円
小・中学生/200円